日々トレーニングに励むアスリートにとって、ケガは最大の敵です。
練習や試合を継続的にこなす中で、違和感や痛みを抱えながらプレーすることは珍しくありません。
しかし、同じ部位の痛みを繰り返したり、慢性的に疲労が抜けなかったりする場合、それは“動作のエラー”が原因になっているかもしれません。
いくら治療やストレッチをしても、痛みの根本が解決していなければ、再発のリスクは常につきまといます。
今回は、アスリートが“ケガをしにくい体”をつくるために活用できる「SFMA」という動作評価法についてご紹介します。
ケガを防ぐには“動作”に注目すべき理由
アスリートの体は常に酷使されています。そのため、どれだけ丁寧にケアしても、体の一部に負担が集中するとケガは起こりやすくなります。
特に、ウォームアップやストレッチ、筋トレに取り組んでいるにもかかわらず不調が続く場合、“正しい動き”ができていない可能性が高いのです。
人間の体は、全身の関節や筋肉が連動して機能します。一部の可動域が制限されていたり、正しく使えていない部位があると、他の部位が代償動作を行い、過剰なストレスがかかります。
こうした代償動作は無意識に起こるため、自覚がないまま長年続いてしまい、やがて痛みやケガとして現れます。
だからこそ、「どの関節が動きすぎているのか」「どこが動いていないのか」といった視点から、自分の動作を見直すことが重要なのです。
SFMAとは?|動作から不調の原因を探る評価法
SFMA(Selective Functional Movement Assessment)は、アスリートを含むすべての人の「動き」を評価するためのシステムです。7つの基本的な動作を行い、その動作が行えるか、そして痛みの有無をチェックします。
大きな特徴は、どこが悪いかではなく、なぜそこが悪くなっているのかを見つけ出せる点にあります。
たとえば、腰に痛みがある場合でも、原因は股関節の可動域の問題だったり、足首の硬さだったりする可能性があるからです。
また、FMSとの違いは、FMSが主にパフォーマンスの予測と予防に用いられるのに対し、SFMAはすでに痛みや不調がある状態に対して原因を特定するために使われるという点です。
つまり、ケガをしてしまったアスリートや不調が続く人にこそ活用してほしい評価法なのです。
アスリートのよくあるパターンとSFMAの活用例
ケース①:腰の疲労が抜けないランナー
中・長距離を走る選手に多く見られる腰の張りや痛み。その原因が股関節の硬さであることは少なくありません。股関節が十分に動かないことで、走行時に腰椎が過剰に動いてしまい、結果として腰に負担が集中します。
SFMAを通して評価すると、前屈やしゃがみ込み動作の中で、股関節の可動域制限や骨盤のコントロール不足が明らかになるケースがあります。
この場合、股関節のモビリティトレーニングや体幹の安定性を高めるエクササイズを導入することで、腰の負担が軽減されます。
ケース②:肩の痛みを抱える野球選手
投球動作を繰り返す野球選手に多いのが、肩のインピンジメント(衝突症候群)です。原因の一つとして、胸椎の回旋可動域の低下や肩甲骨周囲筋のコントロール不足が挙げられます。
SFMAでは、上半身の回旋動作や上肢の挙上動作を評価することで、肩だけでなく、その連動部分までチェックすることが可能です。胸椎や肩甲骨の動きを改善するアプローチを先に行うことで、肩関節への過度なストレスを避け、痛みの再発を予防します。
ケース③:ハムストリングスの肉離れが多いサッカー選手
スプリントやキックの多いサッカーでは、ハムストリングスのトラブルが多発します。しかし、ハムストリングそのものが弱いわけではなく、骨盤の前傾や体幹の不安定性が原因になっていることもあります。
SFMAにより、しゃがみ込み動作や立位での体幹制御を評価し、骨盤の位置関係やコアの使い方を見直します。これにより、ハムストリングの過緊張を抑え、筋損傷のリスクを減らすことができます。
ケガ予防とパフォーマンスアップのためのトレーニング設計
SFMAを導入する最大のメリットは、トレーニングを感覚ではなく“評価”に基づいて設計できることです。
アスリートそれぞれの動作の癖や弱点を可視化し、改善に必要なエクササイズを優先順位をつけて取り組むことができます。
基本的な改善までの道のり
➀可動性の改善
まずは筋柔軟性をはじめ、軟部組織の伸張性を高めて、適正な関節可動域の回復を行います。
正しく動ける体には、柔軟な関節の可動域が必要です。
②安定性の再構築
関節が正しく動くためには、その隣り合った関節の安定性が必要です。
これはJoint by Joint Theoryという考え方に基づいています。
③動作の再教育
動かす感覚を再構築します。
正しく動いている“感覚”と正しく動かせている“感覚”を理解します。
具体的には正しい動きを理解して、その動きを再現できるようにすることです。
この3ステップを軸に構成することで、「ただ鍛える」だけでなく、「効率的に動ける体」を作ることができるのです。結果として、ケガの予防とパフォーマンスアップを両立することができます。
まとめ|“ケガをしにくい体”は評価から始まる
アスリートとして、長く競技を続けるためには、ケガをしない体づくりが必要不可欠です。その第一歩が、“動作の見直し”です。
SFMAを活用することで、痛みや不調の“根本原因”を探ることができ、自分に本当に必要なケアやトレーニングを明確にすることができます。
今のトレーニングに行き詰まりを感じている方、繰り返すケガに悩んでいる方は、一度“動作評価”を受けてみてはいかがでしょうか?
ケガのない体は、動きの質から始まります。
自分の体を知り、正しく整え、強くしていくことで、競技人生をより豊かに、そして長く楽しむことができるはずです。
ケガに悩まされている方、動作評価やSFMAに興味がある方は西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にご相談ください。




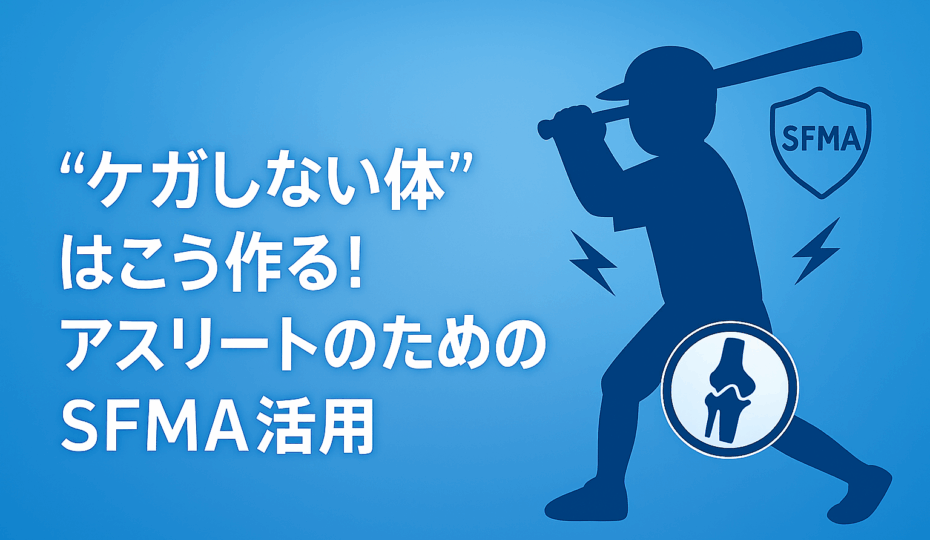

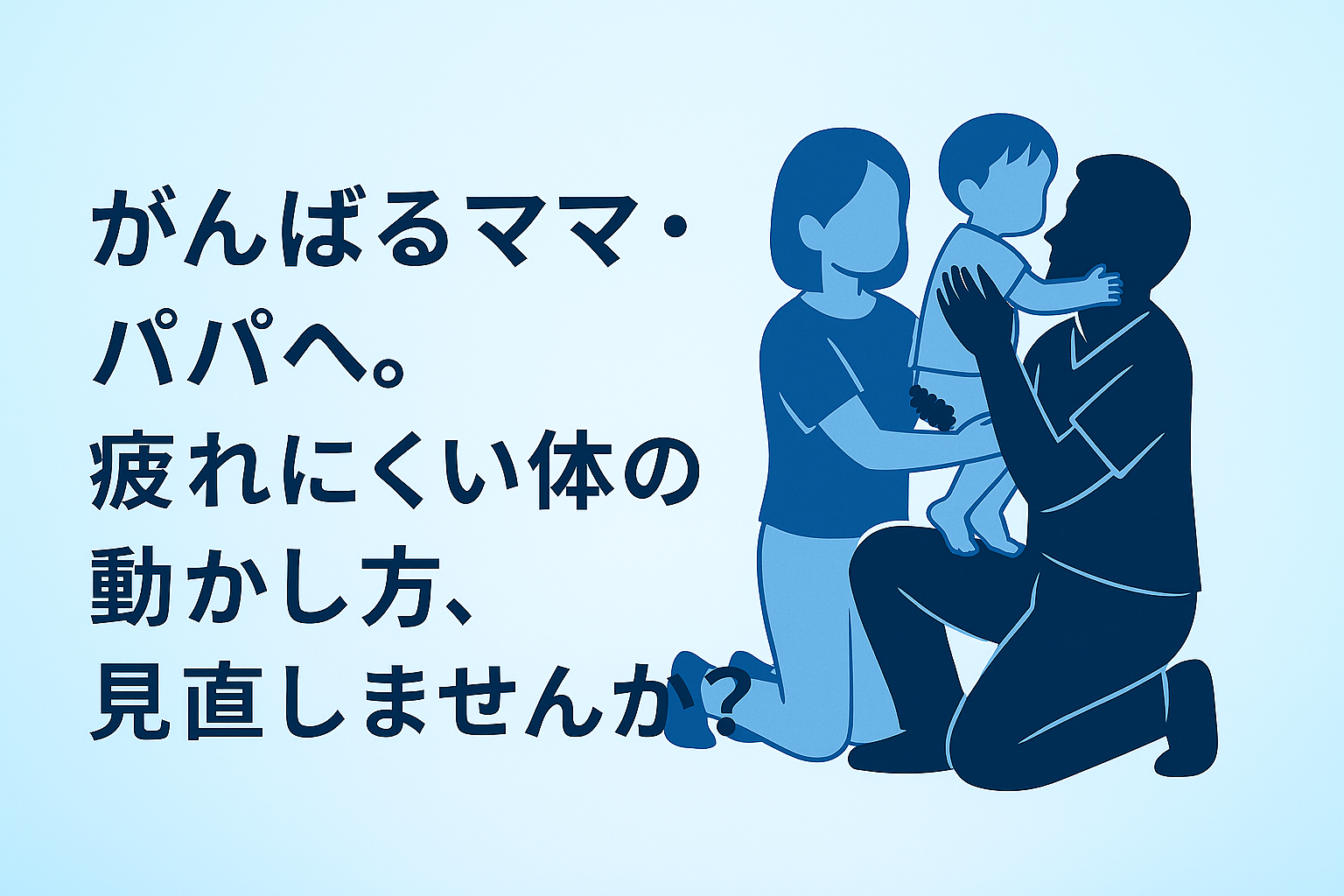















コメント